令和6年から贈与税制度が変わります!
税理士・公認会計士 佐藤 洋平
令和5年度税制改正により贈与税制度が大幅に見直され、令和6年以後に行われる贈与について、「相続時精算課税」制度が使いやすくなりました。
今回は、令和6年からどのような税制となるのか、今後はどのように財産移転をするのが良いのかについて、概要をお伝えします。
Q 贈与税とはどのような税金ですか?
A 贈与税は、贈与者(あげる人)から受贈者(もらう人)に対して財産を贈与した場合に、受贈者に対して、課税されるものです。
贈与税は相続税の補完税です。もし生前贈与を無税で行えると、いくらでも相続税逃れができてしまうため、生前贈与に一定の歯止めをかける趣旨で贈与税が課税されることになっています。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。
Q 「暦年課税」とはどのような制度ですか?
A 「暦年課税」は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与等により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円(=非課税枠)を差し引いた金額に対して、贈与税を課税する制度です。仮に1年間にもらった財産が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
「暦年課税」では、受贈者(財産をもらった人)ごとに計算します。例えば、同一年に両親から100万円ずつもらった場合の受贈額は200万円となり、基礎控除額110万円を差し引いた90万円に対して累進税率(200万円以下は10%)を乗じた9万円を翌年3月15日までに申告納付する必要があります。なお、税率は【図表1】のとおり、「特例税率」(直系尊属から18歳以上の者への贈与のケース)と「一般税率」(その他のケース)の2種類があります。
「暦年課税」には毎年110万円の非課税枠があるため、なるべく早いうちから長期間にわたって贈与を受けた方が有利と言えます。例えば、親から子3人に対して110万円ずつ20年間贈与すれば、累計6600万円の財産を贈与税負担なしで移転可能です。但し、後述のとおり相続財産への足し戻し(加算)ルールがあります。
【図表1】 「暦年課税」の贈与税率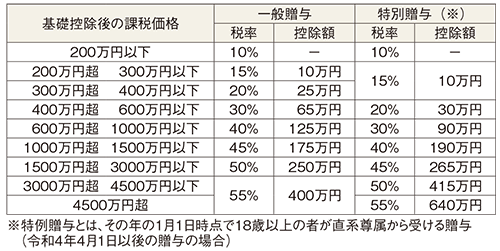
Q 令和5年までの「暦年課税」の足し戻し(加算)ルールについて教えてください。
A 贈与者が亡くなった場合、「暦年課税」で贈与した財産があるときは、死亡前3年以内の贈与額を贈与者(被相続人)の相続財産に足し戻して(加算して)相続税を計算します。なお、年間110万円(非課税枠)以内の贈与であっても加算の対象となる点がポイントです。
加算対象となった贈与財産に対して納付していた贈与税がある場合は相続税額から控除できますが、控除しきれない場合に還付は受けられません。
令和5年までの「暦年課税」のイメージ図は【図表2】のとおりです。
【図表2】 令和5年までの暦年課税制度のイメージ(加算期間3年)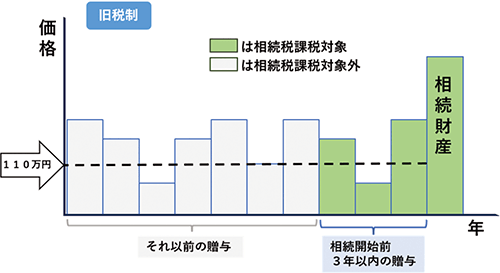
Q 令和6年以後、「暦年課税」の足し戻しルールについて見直しが行われたと聞きましたが、その内容を教えてください。
A 暦年課税における相続前贈与の加算期間を「3年」から「7年」まで順次延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与の合計額のうち100万円については相続財産に加算しないこととする見直しが行われました。この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。
改正後の「暦年課税」のイメージ図は【図表3】のとおりです。
【図表3】 改正後の暦年課税制度のイメージ(加算期間7年の場合)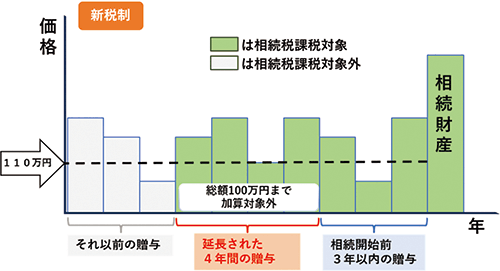
なお、加算期間の延長は、令和13年までにわたり次のように行われます。
- 令和8年12月31日までに贈与者が亡くなった場合
→死亡前3年以内の贈与を加算する - 令和9年1月1日以後に贈与者が亡くなった場合
→死亡前7年以内の贈与を加算する(ただし、令和6年1月1日以後の贈与分に限る)
Q 「相続時精算課税」とはどのような制度ですか?(令和5年までの制度を前提に)
A 「相続時精算課税」とは、贈与時点では贈与税について一定の軽減を行う一方で、贈与者が死亡した際に相続税を計算し、生前に納めた贈与税の精算を行う課税方式です。相続発生時に生前贈与分の贈与税の精算を行うので「相続時精算課税」と呼ばれています。高齢者層から若年層へ比較的高額な財産の早期移転を促すための制度です。
この制度は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などへ贈与を行った場合が対象であり、原則として贈与年の翌年3月15日までに「相続時精算課税」を選択する届出を税務署に提出する必要があります。
この制度を選んだ場合の「贈与時」と「相続発生時」の税負担は次のとおりです。
(贈与時)
贈与時には、累計贈与額2500万円(特別控除額)までは課税されず、2500万円を超えた部分に20%の税率で贈与税が課税されます。「暦年課税」では多額の資産を一度に贈与すると贈与税率が高くなってしまいますが、「相続時精算課税」であれば贈与時の税負担は軽減されます。
なお、この特別控除額(累計2500万円)は複数年にわたり使うことができます。
(相続発生時)
贈与者が死亡した際には、この制度を利用して贈与した累積贈与額(贈与時の財産評価額の累計額)を相続財産に加算して相続税を計算します。なお、この制度によって納付した贈与税額は相続税額から控除され、相続税額から控除しきれない場合は還付されます。
「相続時精算課税」は特定の個人間の贈与について選択するものです。例えば、父から長男への贈与について「相続時精算課税」を選択した場合に、母から長男への贈与についても自動的に「相続時精算課税」が適用されるわけではありません。
なお、「相続時精算課税」を選択した後は、その贈与者から受ける贈与については「暦年課税」に戻れなくなることがポイントです。
「相続時精算課税」では、贈与時における評価額をもって将来の相続発生時に足し戻すため、将来的に値上がりが見込まれる資産(一次的に評価額が落ちている資産など)には向いていますが、将来的に値下がりが見込まれる資産には向いていません。また、高収益物件(不動産など)を持っている場合に将来の相続財産の蓄積を抑えるために贈与するケースや、相続税がかからないと見込まれるケースにおいて早めに生前贈与する際に向いています。
令和5年までの「相続時精算課税」のイメージ図は【図表4】のとおりです。
【図表4】 令和5年までの相続時精算課税制度のイメージ(基礎控除なし)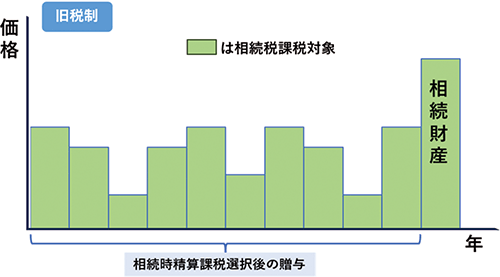
Q 「相続時精算課税」について令和6年からどのように変わるのですか?
A 以下の点が変わります。
- 基礎控除110万円(非課税枠)の創設
令和6年1月1日以後に行う贈与について、「相続時精算課税」においても、贈与財産の課税価格から毎年110万円を控除できることになりました。しかも、この基礎控除額については、「暦年課税」とは異なり、相続発生時に一切加算する必要がないものとされました。具体的なイメージは【図表5】のとおりです。
これまでは、いったん「相続時精算課税」を選択すると、その後はその贈与者から受ける贈与について毎年110万円の非課税枠(暦年課税の基礎控除)が使えなくなるというデメリットがありましたが、今回の改正で「相続時精算課税」でも毎年110万円の非課税枠(基礎控除)が使えるようになった点が大きなメリットと言えます。 - 財産評価の再計算ルールの創設
「相続時精算課税」で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算(贈与時における価額から当該価額のうち災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除)する見直しが行われました。
これまでは、贈与後に土地・建物が被災により被害を受けても、相続財産への足し戻し額について、贈与時点の評価額で固定されていましたが、今回の改正で被災時には評価の見直しがなされることで、以前より不動産を贈与しやすくなったと言えます。
【図表5】 改正後の相続時精算課税制度のイメージ(110万円の基礎控除あり)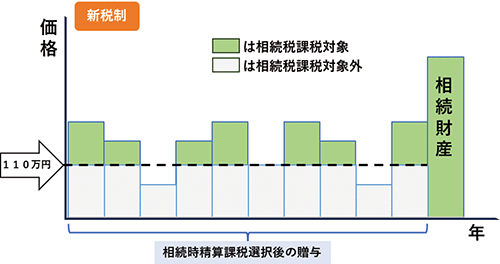
Q 令和6年以降「相続時精算課税」をどのように使うことが想定されますか?
A 例えば以下のような使い方が考えられます。
- 余命が数年内と見込まれる方(高齢者や健康状態に不安がある方など)の場合は、「暦年課税」だと相続財産への足し戻し対象期間(最長7年)にひっかかる可能性があります。そこで、「相続時精算課税」で子どもに毎年110万円の贈与を行うことが考えられます。
例えば、死亡前の7年間、毎年110万円の贈与を子1人に対して行った場合、「暦年課税」だと670万円を相続財産に足し戻さなければなりませんが、「相続時精算課税」だと足し戻し対象額はゼロであり、相続税の課税対象財産額に670万円の差が生じます。 - 「暦年課税」と「相続時精算課税」の非課税枠(110万円)のダブル適用を狙うことが考えられます。例えば、父親の方が母親よりも先に亡くなる可能性が高いと見込まれる場合に、父親からは「相続時精算課税」で毎年110万円の贈与を受け、母親からは「暦年課税」で毎年110万円の贈与を受けることで、合算で年間220万円の贈与を非課税で受けることができ、相続税の軽減につながります。
- 親が所有している高収益の不動産を早めに「相続時精算課税」を使って子に贈与したうえで、毎年110万円(非課税枠以内)の贈与も行うことで、不動産から得られるキャッシュフローを早めに子に移転でき、親の相続財産の増加を抑えることができます。なお、この対策は親が認知症となるリスク(不動産の大規模改修、建て替え、売却などの意志決定ができなくなるリスク)への備えとしても有効です。
ただし、土地を贈与した場合はその土地について小規模宅地の特例(一定の条件を満たす土地を相続した場合の相続税計算上の評価減)が使えない点や、不動産取得税・登録免許税も「贈与」の方が「相続」よりも税率が高いことに注意が必要です。
まとめ
以上のとおり、令和6年1月より「暦年課税」のメリットが減った一方で「相続時精算課税」が使いやすくなりましたが、「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれが有利かはケースバイケースです。受贈者(子など)が先に亡くなった場合に相続税が二重課税になるケースがあることなど、実際の活用については慎重な検討が必要です。また、特定の相続人にのみ生前贈与を行うと、いわゆる「争族」問題に発展しやすいため、遺言書の作成なども含めた多面的な検討が必要となります。
相続はいつか誰にでも起こるもの。だからこそ、トータルバランスの取れた円満な相続となるよう、前もって専門家(税理士、弁護士、司法書士等)にご相談することをお勧めいたします。
さとう ようへい (文)
Yohei Sato
税理士・公認会計士
佐藤税理士法人 代表社員
(公社)日本医業経営コンサルタント協会 岩手県支部長
医業承継・M&A、開業支援業務に多数従事