第20回
体感温度は室温より放射温度で考えたい──という考えにくさ。
編集者 加藤 大志朗
熱の伝わり方には
三つの種類がある
温度計の温度はさほど高くないのに、日射しの強い窓際などにいると暑さを感じ、日の当たらない場所では寒さを感じる。これは、熱が伝わる仕組みの違いによるものです。
熱の伝わり方には、大別して伝導・対流・放射など三つの種類があります。
フライパンを火にかけると、取っ手まで熱くなります。これは直接火が当たる底の部分から取っ手まで熱が伝わった「伝導」。浴室の温度が低いと、その温度がお湯に伝わり、お湯が冷めてしまうのも「伝導」といえます。
「対流」は気体や液体が熱せられることで、軽くなって上へ移動し、冷たい部分は下降して熱が動くこと。寒い浴室でお湯が冷めるのは「伝導」に加え、お湯が水蒸気となって上昇し、冷たい空気が下降する「対流」も影響しています。
日射やたき火、炭焼きなどの熱が、寒い屋外でも暖かく感じるのは「放射」によるもの。「輻射」ともいわれ、辞典を引くと「気体、液体または固体を構成する原子や分子から、温度に依存する電磁波が放出されていること」とあります。
そもそも太陽光も電磁波で、壁や床や天井、自分の身体からも電磁波が「放射」されています。温度のある風が吹いてくるわけではないのに、ふわっと暖かい感覚です。
熱カメラ(サーモグラフィー)で撮影した画像を見たことがあると思いますが、あれは物体から「放射」される電磁波を温度の高い順から赤や黄、緑などの色で示したものです。
暖かい「環境」と
寒くない「環境」
私たちが家で暖冷房を調整する際、温度計の温度だけで「快適さ」を判断しようとします。
温熱環境の「快適さ」とは、一言でいうと寒くないこと、暑くないこと。湿度や着衣の質・量、活動量なども関係します。
湿度や隙間風などの気流により快適さが異なるのは誰しも経験したことがあるはず。快適な温熱環境を考える際、温度ではなく「体感温度」が重要な指標とされるのはそのためです。
冬は、24時間連続して暖房設備を運転することで壁、天井、床、家具などに熱が溜められます。夏はすだれやカーテンなどで日射遮へいをした上で、冷房を連続運転することで壁、天井、床、家具などの温度の上昇を抑え、快適さを維持できます。どちらも、「放射」される熱をコントロールしているわけです。
連続運転というと「省エネに逆行する」という反論がありそうですが、就寝時や外出時などに暖冷房をオフにすることで、壁、天井、床、家具などの表面温度が上下してしまい、運転再開時、壁、天井、床、家具などの温度がもとに戻るまで時間を要します。
2011年に電力中央研究所が行った実験では、170分のテスト時間内の消費電力量を計算したところ、小まめにオン・オフを繰り返した間欠運転の方が、連続運転より約30%消費電力が多くなったという結果が出ています。この実験からすでに10年が経過していますが、現在の家の方が断熱・気密性能が向上しているとすれば、連続運転の方がより効率的な省エネ運転が可能であるといってもよさそうです。
参考までに、これまで取材をしてきた平均的な高性能住宅(※UA値0.46W/㎡・K C値0.5㎠/㎡前後)でオール電化仕様(ヒートポンプ温水暖房・エアコン・エコキュート・IHクッキングヒータ採用)で、冬期は24時間全館暖房、夏期は24時間全館冷房としても年間の電気代は18万円前後。そうでない住宅の全国平均が約21万円ですので、温熱環境が快適になってもエネルギー消費は高くならないことが分かります。
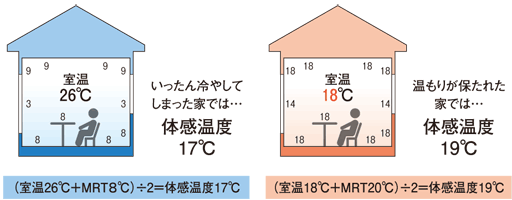
足の指10本全て
しもやけになる
終日、屋内のどこでも「寒くない」「暑くない」温熱環境が得られることで、病院や施設のような介護に適した環境が実現できます。急激な温度差で引き起こされるヒートショックの予防効果も高まるはずです。限りなく少ないエネルギーでこうした環境を得るために、断熱・気密性能の担保が必要なのです。
私は北海道で生まれ、高校を卒業するまで北海道で育ちましたが、厳寒期を裸足で暮らしても、しもやけになったことはありません。北海道では伝統的に就寝後も種火を絶やさない生活がふつうで、半世紀以上前でもコタツを使う家もなかったのです。いまと比べると、家の断熱性能は貧弱でしたが、小さな火を絶やさず、寒い時間帯をつくらない=家を冷やさない手法がすでに根付いていたのかもしれません。
伝統的なアイヌの家「チセ」は、丸太3本の支柱を上で合わせて束ねた上に茅葺きをし、床は1メートルほど掘った構造です。室内の真ん中に囲炉裏が設けられ、火は24時間・365日絶やしてはならないのが決まりでした。
夏の間、太陽で暖められた地熱が、半年に及ぶ冬の間、ちょろちょろと燃える囲炉裏の火で周囲の壁、床などから引き出され、屋内に「放射」されます。夏は逆に、冬の間、土に蓄えられた冷たさを引き出し、冷涼な環境に近づけます。そこには、暖炉やペチカを連続運転させて石やレンガに熱を溜め、そこから「放射」される熱を活用する欧州の暖房文化に共通するものを感じます。
話は戻りますが、私はその後、縁あって岩手県出身の女性と結婚し、30数年前に盛岡に移住。当時住んだ安アパートでは、開放式の灯油ストーブ1台の暮らし。安全面から就寝時は火を消して寝るほかはなく、いわゆる間欠暖房の環境でした。
そして迎えた初めての冬。私は生まれて初めて両足の指10本がしもやけになってしまいます。この経験が、日本の住宅の温熱環境と居住福祉との関係を学ぶきっかけとなったのでした。
かとう だいしろう (文・写真)
Daishiro Kato
1956年北海道生まれ。編集者。これまでに25カ国を訪れ、国際福祉・住宅問題などの分野でルポや写真、エッセイを発表。住宅分野では30年以上にわたり、温熱環境の整備と居住福祉の実現を唱えてきた。主な著書に『現代の国際福祉 アジアへの接近』(中央法規出版)、『家は夏も冬も旨とすべし』(日本評論社)など。出版・編集を手掛けるリヴァープレス社代表(盛岡市)。
 屋内に温水パネルヒーターを分散し、全館を連続暖房する。パネルの表面はふれても火傷をしない程度の温度。気流も発生せず「寒さが取り除かれた」理想の暖房感。躯体の断熱・気密性能を向上すればするほど、設備投資もランニングコストも安くなる。
屋内に温水パネルヒーターを分散し、全館を連続暖房する。パネルの表面はふれても火傷をしない程度の温度。気流も発生せず「寒さが取り除かれた」理想の暖房感。躯体の断熱・気密性能を向上すればするほど、設備投資もランニングコストも安くなる。
※UA値=外皮平均熱貫流率
住宅の内と外の温度差が1℃ある場合、建物内部から逃げる1時間あたりの熱量を外皮等の面積の合計で割った値で、躯体を構成する部位の「熱の伝わりやすさ」を表わす。数値が小さいほど、断熱性能が高い。0.46W/㎡・Kという性能は、北海道などの寒冷地の基準値。
※C値=相当隙間面積
住宅全体の隙間を床面積で割った数値。数値が小さいほど、気密性能の高い住宅といえる。気密測定器で実測が可能。