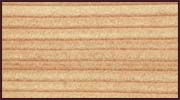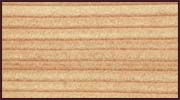|
| すぎ科の常緑高木。真っ直ぐな幹を持つ。日本特産。材質は柔らかで木理が真っ直ぐで割りやすい。建築材として多く用いられ、建具材・電柱・家具・桶樽材・箸に至るまで幅広く使用されている。 |
|
 |
 |
| ごまのはぐさ科の落葉高木。南部桐は最良材として有名。収縮・膨張が小さく、狂いが少ない。吸湿性が低く、断熱性、耐久性に富む。履物・建具・家具・楽器材として利用されている。 |
|
 |
 |
| ぶな科の落葉高木。材質は堅く、弾力、反張力に富む。水潤に強く、耐久性も大きい。鉄道の枕木・家屋の土台・家具材に利用される。また、薪炭材として多く用いられている。 |
|
 |
 |
| まつ科の常緑高木。南部あかまつは岩手の県木。重硬で強度が高いが、加工性は良好。ただし樹脂成分が多い。主に建築・土木資材として利用され、パルプ材や松炭にも用いられる。樹脂はテレピン油となる。 |
|
 |
 |
| うこぎ科の落葉高木。大径木になる。材質は艶があり、加工性がよい。大きな板が得られ、木目が美しい。内装用材・家具材・合板用材・工芸品など広く利用されている。 |
|
 |
 |
| (オニグルミ)くるみ科の落葉高木。独特の光沢を持ち、軽軟で加工性がよく、割れや狂いが少ない。造作材・内装材・家具などに利用される。樹皮はよい染料となる。 |
|
 |
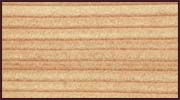 |
| まつ科の落葉高木。適地適木として岩手県北に多く造林された。日本特産。材質はやや重硬で強度が高いが、利用の仕方によっては割れや狂いが出やすい。主に建築・土木資材に利用。また、家具材、外構材としても用いられる。 |
|
 |
 |
| ぶな科の落葉高木。大径木になる。材質は緻密で堅く、加工性がよい。反面、利用の仕方によっては変色や狂いを生じやすく、耐久性は極めて小さい。床材・家具材・合板材に利用される。 |
|
 |
 |
| (イタヤカエデ)かえで科の落葉高木。特有の絹糸光沢を持ち、波状杢・縮杢などの杢目を現す。床板・床柱・家具・楽器などに用いられる。また、漆器木地としても利用される。 |
|
 |
 |
| にれ科の落葉高木。北東北がその北限で日本を代表する樹木。社寺の構造材、造作材全般に利用。木目が美しく、家具や工芸品に多く用いられ親しまれている。 |
|
 |
 |
| (ミズナラ)ぶな科の落葉高木。用材としては主にミズナラを使用する。材質は緻密で重く、木目が美しい。床材・家具・化粧単板・枕木材などに利用される。また、小径木は薪炭材として多く用いられる。 |
|
 |
 |
| かつら科の落葉高木。大径木となる。材色が濃いものをヒガツラ、淡いものをアオガツラと呼ぶ。軽軟で反りにくく、加工性がよい。器具材・家具材・化粧用単板に用いられる、彫刻材や碁・将棋版などにも利用される。 |
|